
2025年7月13日にステーションコンファレンス東京にて、ピジョン奨学財団の新奨学生発表会・交流会が行われました。小児科、産科、新生児科の医師を志す学生を対象に奨学金を支給するピジョン奨学財団は、2014年に設立され、11年目となります。今年は北海道から九州まで全国の大学医学部5年生50名が新たな奨学生として選抜されました。今年度を含めて485名のピジョン奨学財団奨学生が、これまでに誕生したことになります。
新奨学生発表会は、奨学生とピジョン奨学財団の評議員・理事・監事・選考委員が一同に集う形で開催されました。新奨学生は50名中39名が参加。同じ志を持つ奨学生同士が、お互いの顔と顔を合わせてつながりを作る貴重な機会となりました。
第一部:新奨学生発表・奨学生証授与式
まずはじめに、業務執行理事の板倉正より挨拶がありました。

「奨学生の認定、おめでとうございます。ピジョンは60年以上の歴史がある企業です。存在意義を“赤ちゃんをいつも真に見つめ続け、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にします”と掲げ、商品やサービスで子育てを支援しています。奨学生の皆さんは、命を助けたり、子どもやご家族の心に寄り添っていく存在になっていくことでしょう。ピジョンはこれからの時代の出産、育児、子どもの成長などを、みなさんと一緒にサポートしていきたいと考えています。
また、ここで得た同期や先輩たちとのネットワークは、必ず将来の助けとなります。この機会にコミュニケーションを取り、良いネットワークをつくってください。」
続いて、評議員の仲田洋一より祝辞がありました。

「暑い中、多くの奨学生の皆さんにお集まりいただき、御礼申し上げます。この会を開催する大きな目的は、皆さんに横のつながりをつくっていただくこと。将来大きな力になるので、ぜひこの機会を活かしてください。
また、今日は皆さんの今後の助けになるような、ぜひ読んでほしい本を用意してきました。本日の交流会だけでコミュニケーションを取るのではなく、奨学生の皆さんの間で本を回すことで、コミュニケーションを深めるきっかけにしてほしいと思います。」
次に、板倉業務執行理事より新奨学生50名の発表が行われ、一人ひとりの大学名と名前が読み上げられました。発表後に50人の奨学生を代表して、2人に奨学生証が授与されました。




評議員・理事・監事・選考委員より、新奨学生への期待と激励を込めたお祝いの言葉をいただきました。祝辞の一部をご紹介します。





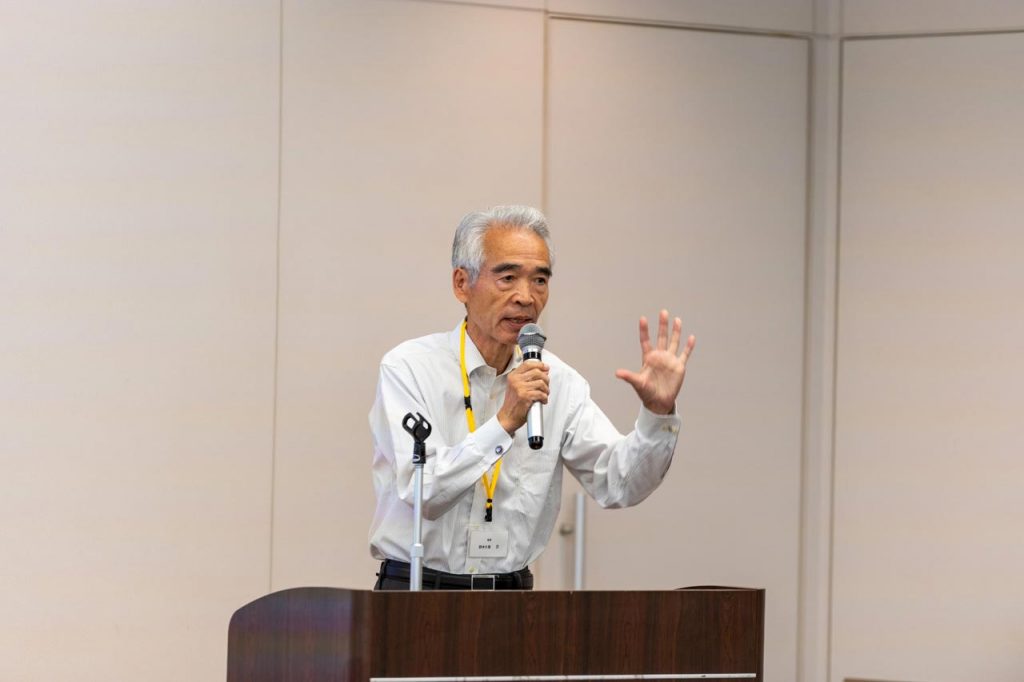

「医師という職業の幅は広く、さまざまな分野で自分を活かすことができます。しかし、どの分野に行っても大切なのはイマジネーションです。症状がどのように変化していくのか、想像しながら先手を打っていけば病気に勝つことができます。逆に、急変して症状を追いかけるようになったら病気に負けてしまいます。想像力を持つことを大切にしてください。」(小児科医/片山啓評議員)
「医療業界の人材育成と組織づくりに関わっていますが、今の医療はネットワークで動いています。組織内のさまざまな部署や、組織内外の医師同士の連携が非常に重要で、たとえどんなに個人が優秀でも、連携ができないと機能しません。皆さんは今後リーダーとなるべき人材だと思いますので、どのように連携してチームを動かすか、リーダーシップを重要なスキルだと認識して、経験を積んでほしいと思います。」(髙田誠評議員)
「毎朝新生児の診察をしていますが、そのたびに『この赤ちゃんたちは、生涯でどのくらいの税金を払うことになるんだろう?』と考えてしまいます。少子化が進む一方で寿命も延びているので、今の赤ちゃんたちは自分より年上の人を何人も支えなくてはならない。私自身も、予防接種の数が少しずつ減っていて、少子化の影響を感じています。小児科医は厳しい環境にありますが、逃げずくじけず、これからの社会をつくっていく赤ちゃんをサポートしてください。」(小児科医/林良寛理事)
「奨学金は皆さんにとって大きな支援です。私自身は奨学財団のお金の使い方をチェックする仕事をしていますが、奨学生の皆さんの使い方をチェックすることはありません。将来の目標に向かって有意義に使ってほしいと思います。」(弁護士/榎本英紀監事)
次に、新奨学生を代表して2名から、ピジョン奨学財団の奨学生としての決意表明の挨拶がありました。

「私は22年前に875gの極低出生体重児として生まれ、4ヵ月間NICUで育ちました。高校1年の冬、当時お世話になった先生の案内でNICUを見学する機会に恵まれ、ひとりの赤ちゃんを救うために何人もの医師が関わっていることを知りました。多くの人のおかげで今の自分があることを実感し、新たな生命を守る医師になることが明確な目標となりました。目標に向かってこれからより一層励むことを誓い、ご挨拶とさせていただきます。」(東邦大学5年)

「子ども食堂でボランティアをしていました。さまざまな環境の子どもと触れ合ううちに、すべての子が当たり前に成長できる社会であってほしいと考え、医療の現場から子どもたちの未来を支えたいと、小児科医を志しました。将来は、家族に寄り添い安心感を与えられる医師になるとともに、海外と日本の橋渡しができる存在になりたいと考えています。ピジョン奨学財団奨学生になったことで、同じ志を持つ仲間と交流できることをとてもうれしく思います。目指す医師像に向けて、切磋琢磨していきたいです。」(新潟大学5年)
第一部の最後には、新奨学生と役員で記念撮影を行いました。多くの奨学生に参加していただいたので、一枚に収まるポジションを決めるのに少し時間がかかりましたが、その際のやり取りで笑いが起こり、緊張気味だった奨学生たちもリラックスできたようです。笑顔がいっぱいの写真を撮影することができました!

第二部:近況報告・交流会

第二部は、昨年から奨学生となっている6年生16名が参加。二部から駆けつけていただいた財団の役員の方も含めて、情報交換や交流を深めるプログラムを実施しました。まずはあらかじめ決められたテーブルにつき、グループごとに自己紹介などの歓談を行いました。乾杯の音頭は、山中選考委員にお願いしました。

「今年の4月、国際学会に参加した際に、ピジョン奨学財団の卒業生と交流することができました。これらも学会や医療現場で皆さんと絆を深めていくことが楽しみです。奨学生の皆さんの未来に乾杯!」




しばらくの歓談の後、全員を前に自己紹介を兼ねた近況報告を、参加した6年生、5年生が1人ずつ行いました。抜粋してご紹介します。
「奨学金を利用して、2月と5月にアメリカに留学しました。小児外科の手術を見学させてもらったり、有意義に過ごすことができました。」(6年)
「4月にイギリス、5月にアメリカに奨学金を活用して留学しました。医療制度など日本と違うところが多く、貴重な学びになりました。」(6年)
「新しいことを始めたいと思い、英語のディベートに取り組んでいます。2月の全国大会で2位になりました!」(6年)
「2週間ほど前に、甥っ子が生まれました。今日も実家でミルクをあげてきました。もちろん、ピジョンの哺乳びんです!」(6年)
「交流会で出会ったピジョン奨学財団奨学生と、仙台、大阪、名古屋の学会で再会することができました。全国の仲間たちとつながることができる貴重な場だと、改めて感じました。」(6年)
「参加した学会で、ピジョン奨学財団奨学生の仲間が最優秀賞を受賞していました。ピジョン奨学財団奨学生はやっぱりすごいです!改めてこのつながりを大切にしたいと思いました。」(6年)
「英会話講師のアルバイトをしています。本日は、英検の二次試験当日です。教え子たちの合格報告を楽しみにしています。」(5年)
「学士入学で医学部に入りました。5月末に2人目の子どもが生まれ、ピジョンさんにはいつもお世話になっています。さらに、小児科希望ですが、小児科の先生方にもお世話になっています。志の高い皆さんとたくさん交流して、刺激を受けたいと思っています。」(5年)
「ピアノが趣味で、病院で演奏したりしています。皆さんと話をしたら、楽器をやっている人も多かったので、ぜひ競演したいです。」(5年)
「奨学生の皆さんの話を聞いていると、志の高い人ばかりで刺激をもらっています。奨学金で心と時間に余裕ができたので、来年2月にタイに留学する予定です。」(5年) この他にも、同じサマースクールに行く予定があることが判明したり、マラソンや音楽など趣味を報告し合ったり、早くもつながりが生まれていることが感じられた近況報告となりました。留学を予定している奨学生も多く、今後の交流会での報告が楽しみです!




近況報告の後の歓談では、交流を深める時間をたっぷり取ることができました。最後にピジョン株式会社執行役員の田窪伸郎評議員より閉会挨拶がありました。

「これだけ多くの人に貴重な時間を割いてお集まりいただき、感謝いたします。日本の医療業界の将来は明るいなと思いながら、奨学生の皆さんのお話を聞かせていただきました。これから難しい局面に直面することもあると思いますが、一生付き合うことができる50人の仲間が心の支えになります。ぜひ立派な医者になってください。」
ピジョン奨学財団は周産期医療の医師を目指す学生を経済的に支援するだけでなく、志を同じくする仲間との交流の場を提供することも大切な役割と考えています。今後も定期的に顔と顔を合わせて交流する場を設け、奨学生同士のネットワークづくりを支援してまいります。今回の交流会では、日本全国で奨学生仲間同士で再会し、交流を深めたとの報告を聞き、とてもうれしく思いました。奨学生の皆さんがこの日に出会った仲間とのつながりを大切に、一人ひとりの目指す医師像に向けて切磋琢磨していくことを願っています。
